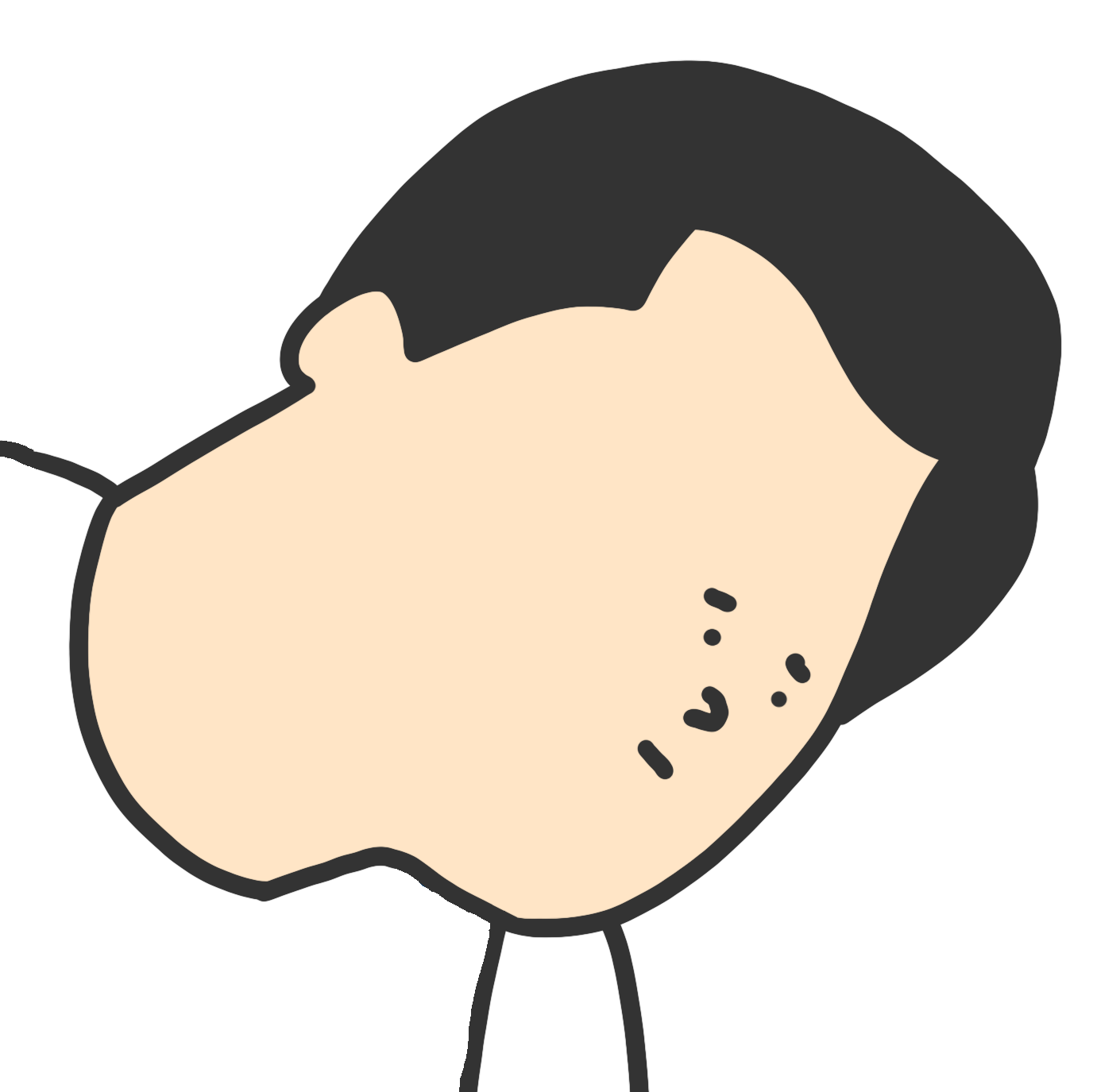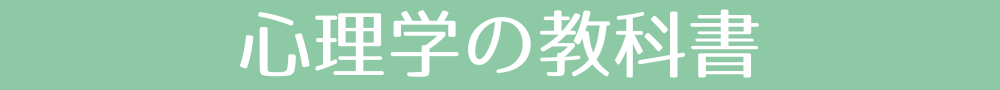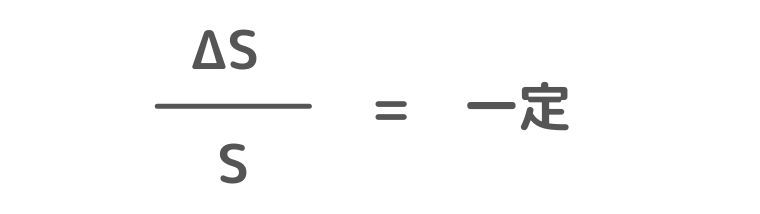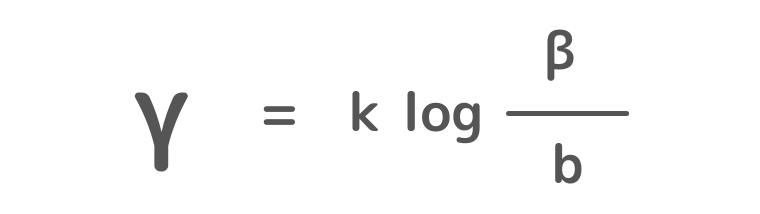このように同じ量(1%という数量)でも、人間は状況によって感じ方が違います。
感じ方=あいまい=測定不可能。。。
18世紀の偉大な哲学者カントも、「心理学は科学にならない」と言ったほどです。
しかし、1850年頃この考えを見事にくつがえす法則がうまれました。
それが「ウェーバー=フェヒナーの法則」です。
いったいどんな法則なのでしょうか。一緒にくわしく見ていきましょう。
ウェーバーの法則
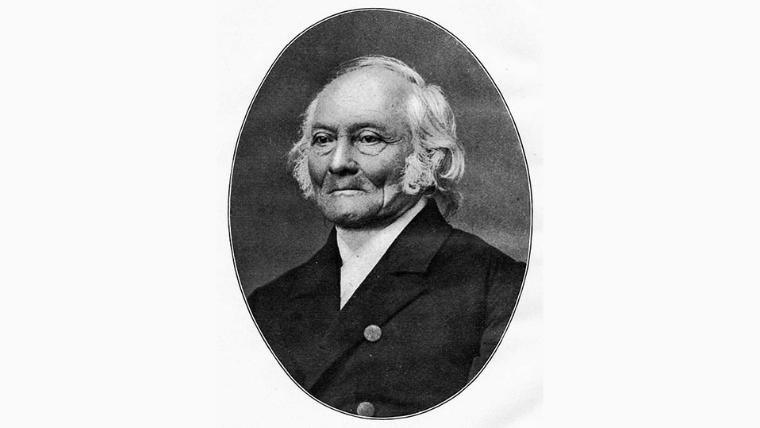
▲「ヴェーバー」1795- 1878(Wikipedia)
ドイツの生理学者ウェーバーは、「重さの感じ方」についてこんな実験をおこないます。
ウェーバーの重さの実験

1、実験者の手のひらに重りをおきます。
2、ほんの少しづつ重りを増やしていきます。

簡単にいうとそんな実験です。
実験①
最初が10gの場合(標準刺激10g)
10gのおもりを持たせる。
↓
(じょじょに重くしていく)
↓
11gになる

実験②
最初が100gの場合(標準刺激100g)
100gのおもりを持たせる。
↓
(じょじょに重くしていく)
↓
110gになる

結果
「重くなった!」と気づく最小の重さは、実験①は「1g」だったけど、実験②「10g増」だった。
この実験でウェーバーは、
「感じる量は、新しい刺激が加わった時、もとの刺激の量に応じて変化する」
ということを発見しました。
ウェーバーの法則の公式
これを数式化したものがこちらです。
これが「ウェーバーの法則」と呼ばれ、心理学における世界初の数量化された法則となりました。

フェヒナーの功績
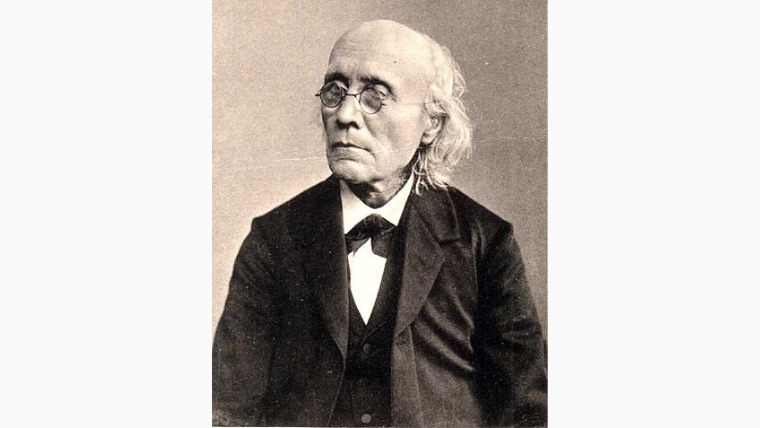
▲「フェヒナー」1801-1887(Wikipedia)
さらにフェヒナーは「ウェーバーの法則」発展させます。

「感覚の大きさ」を加えた
ウェーバーの法則が刺激間の関係に過ぎなかったのに対し、フェヒナーはそこに「感覚の大きさ」をくわえました。
「ウェーバー=フェヒナーの法則」とは
フェヒナーが考えた数式がこちらです。
これが「ウェーバー=フェヒナーの法則」(フェヒナーの法則)です。
ちょっと、むずかしいので詳細は割愛しますが、
「感覚の大きさは刺激量ではなく、刺激量の対数に比例して知覚される。」
ということを、この公式はあらわしています。
閾値の分析と測定方法
ある現象を引き起こすのに必要な刺激の大きさを表す値を、「閾値(いきち)」といいます。
フェヒナーは、この閾値の分析を繰り返しおこないました。
そして人間が刺激を認識できる最小の刺激強度を、絶対閾(刺激閾)と呼び、強さの変化を認識できる最小の刺激強度を、弁別閾(丁度可知差異)と区別しました。
この閾値を決定するために、当時フェヒナーが考案した測定方法は、現代の心理学実験でいまだに使用されています。
まとめ
このようにウェーバーとフェヒナーは、人間の感覚が、「数値」で表現できることを示しました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
ウェーバー=フェヒナーの法則
- 心理学初の数量化された法則
- 丁度可知差異/標準刺激=定数
- フェヒナーが発展させた。
- 「感覚の大きさ」をくわえた。
●ウェーバーの法則
●ウェーバー=フェヒナーの法則
フェヒナーは心と身体の関係を数量で表す、「精神物理学」の創始者であり、のちの心理学に数多くの影響を与えました。
例えば心理学の創始者とされるヴントも、この法則あってこそ、といっても過言ではありません。
あわせて読む
-

-
心理学はいつはじまったのか?現代心理学の創始者「ヴント」とは。
心理学の父「ヴント」の活躍と功績をまとめました。
続きを見る
以上。「ウェーバー=フェヒナーの法則」についてのお話でした。
ご参考にさせていただいた書籍
本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。