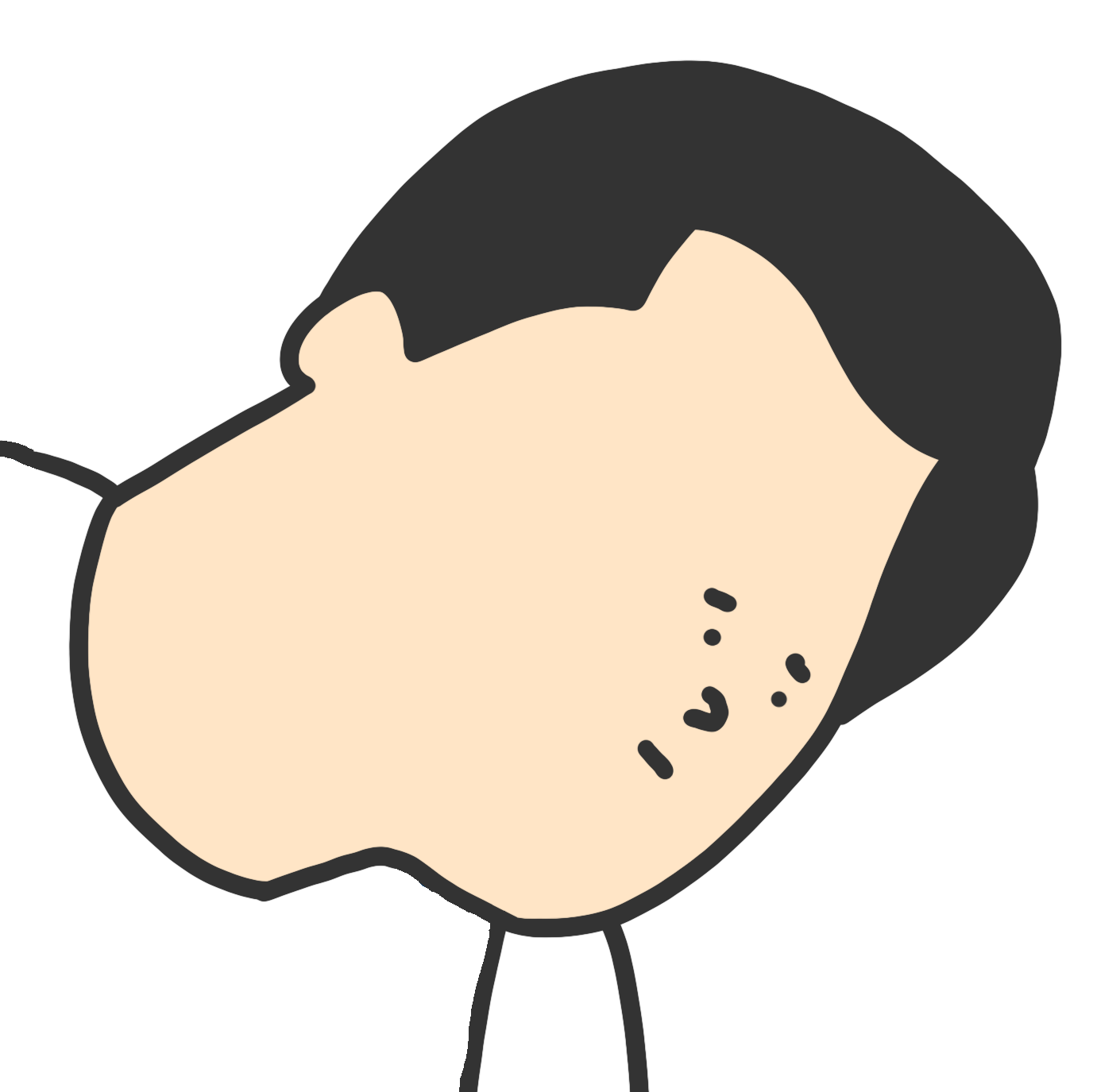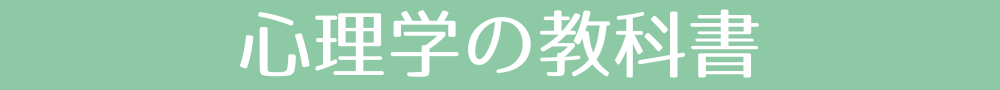心理学用語
広汎性発達障害
Pervasive developmental disorder
頭文字をとって「PDD」と略されることもある「広汎性発達障害」。
いわゆる発達障害のひとつに位置しますが、DSM-Ⅳまで使われていた名称でDSM-5では、「自閉スペクトラム症」に統合されました。
あわせて読む
-

-
自閉スペクトラム症。「三つ組」「スペクトラム」「自閉」とは?
自閉症スペクトラムとは?
続きを見る
とはいえ現時点「広汎性発達障害」も、そこに含まれる「アスペルガー障害」等も、いまだよく耳にする用語となっています。
ということで本日は、この「広汎性発達障害」を理解するために、
- 広汎性発達障害に含まれる障害。
- なぜDSM-5で変更されたのか。
この2点を中心に一緒に確認していきたいと思います。
広汎性発達障害に含まれる障害
「広汎性発達障害」には、以下の下位分類があります。
- 自閉性障害
- アスペルガー障害
- レット障害
- 小児崩壊性障害
- 特定不能の広汎性発達障害
自閉性障害
児童精神科医カナーが提唱したもので、
「対人相互反応の障害・コミュニケーションの障害・限局された興味関心」の3つの行動特徴が、「3歳ごろまで」に明確に認められることが定義されました。
またカナーの自閉性障害では、知的障害のないケースは少ないと考えられていました。
この知的障害をともなわない場合を「高機能自閉症」と呼び区別することもあります。
アスペルガー障害
コミュニケーションの障害が少なく、知的能力に困難がない場合をアスペルガー障害としました。


レット障害
女児のみが発症するレット障害。
5ヶ月頃までは正常に発達していくが、4歳頃に頭部の成長が減速し、重度な精神遅延と自閉症傾向をもつようになる障害です。

小児崩壊性障害
2歳頃まで正常に発達していくが、3歳以降発達が停止し退行していく障害です。
特定不能の広汎性発達障害
上記で見てきた基準を満たさない広汎性発達障害のことです。

なぜDSM-5で変更されたのか
広汎性発達障害はDSM-5以降、自閉スペクトラム症に統合されました。


区別が困難だったから
理由の一つとして、厳密な区別が困難だったことが言えます。
上記のように、広汎性発達障害にはさまざまな下位カテゴリーがありましたが、実際はそれぞれの概念には重複があったのです。
例えば、「どの程度の言語障害がアスペルガー障害なのか?」だったり、「アスペルガー障害は高機能自閉症とどう区別するのか?」などは未整理のままでした。
診断にも諸説が生まれるという、混乱を招いてしまう原因ともなったのです。
日々変化があるから
実際の症状は、周囲の環境や対応・養育の仕方によって困難が重くなったり、軽くなったり変化します。
そのため、単純にカテゴリーの枠に当てはまらない場合が多くありました。
この場合、診断名で障害を判断することはプラスにはならず、むしろ子どもの個々の姿を見失ってしまうという危険性があったからなのです。
「自閉スペクトラム症」への変遷
このような理由により2013年DSM-5の発表以降、広汎性発達障害は「自閉スペクトラム症」に統合されることになりました。
なお「スペクトラム」とは連続したものという意味で、明確な境界線がない大きな枠組みになります。
これはウイングの提唱した概念で、日々変化する子どもの様子を見守りながら、柔軟に適切に対応していこうという姿勢がそこには表れています。
あわせて読む
-

-
自閉スペクトラム症。「三つ組」「スペクトラム」「自閉」とは?
自閉症スペクトラムとは?
続きを見る
まとめ~広汎性発達障害~
最後に、広汎性発達障害についてポイントのおさらいです。
広汎性発達障害のポイント
- 広汎性発達障害=PDD
- 自閉性障害・アスペルガー障害を含む。
- 自閉スペクトラム症に統合
- 理由①区別が困難
- 理由②日々変化するから
- 自閉スペクトラムは連続体
- 変化する様子を見守る姿勢
以上、広汎性発達障害についての解説でした。
ご参考にさせていただいた書籍
本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。