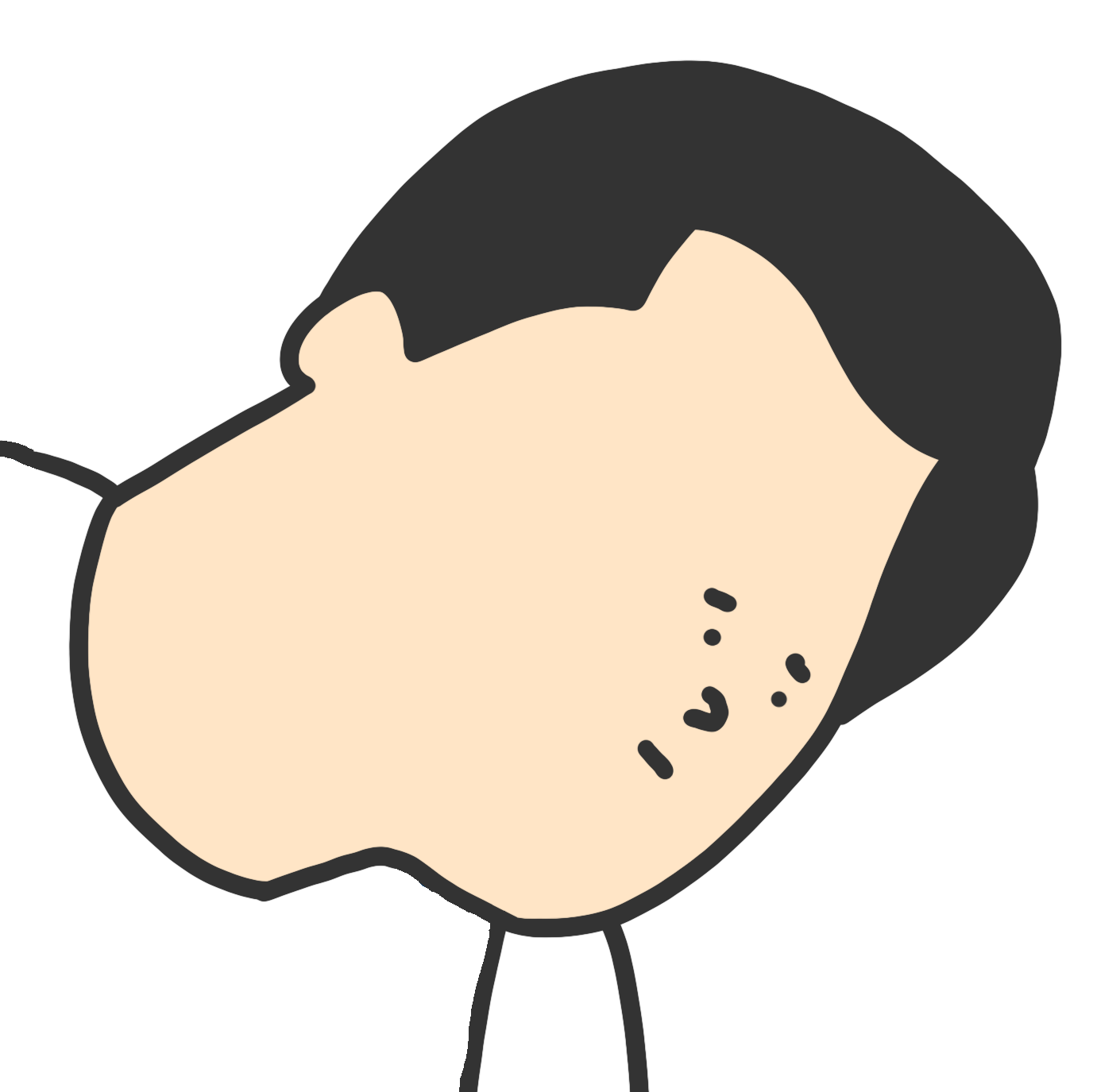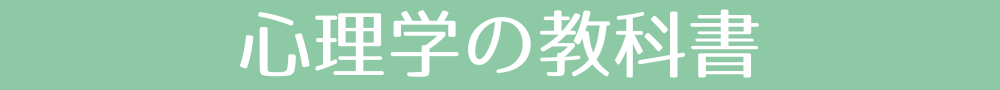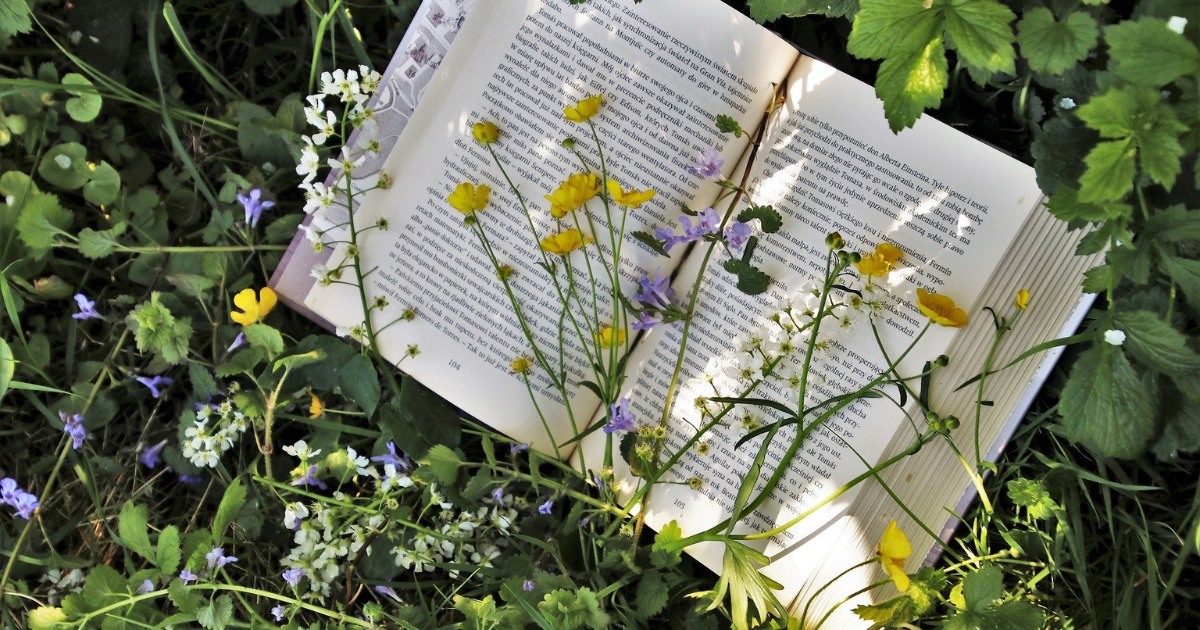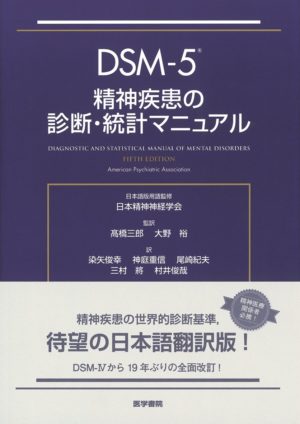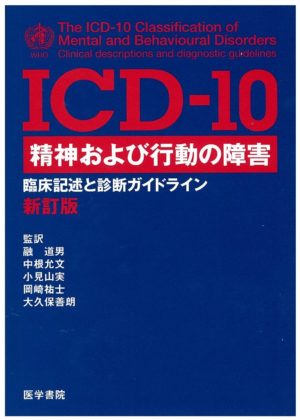心理学用語
DSM
「DSM」とは、アメリカ精神医学会による「精神疾患の分類と診断の手引き」の略称です。

初版である「DSM-Ⅰ」が作成されたのが1952年。
現在は第5版である「DSM-5」が発表されています。
DSMのおかげで、精神疾患の分類はより客観的になり、診断のばらつきも少なくなりました。

というわけで、今回はこのDSMをくわしく見ていきましょう。
DSM以前

DSM以前の精神疾患の診断は、医師の主観の影響が大きく、客観性に乏しいという限界をもっていました。
クレペリンの分類

E. Kraepelin 出典:Wikipedia
クレペリンは、精神疾患の原因に注目する考え方「病因論」にもとづき精神疾患を以下の3つに分類しました。
- 外因性
- 内因性
- 心因性
❶外因性
外部環境から加えられた身体要因(脳の損傷や服薬)により生じた症状。
❷内因性
遺伝的な身体要因によって生じた症状。
❸心因性
身体要因ではなく、心理的な要因によって生じた症状。

さらには、「内因性で、なおかつ心因性でもある」など原因が複数にまたがる場合も考えられます。
このように、病因論では厳密な分類はむずかしく、現在は積極的に使われていません。
病態水準

「病態水準」とは、精神症状の「重篤さ」を3レベルに分類する方法です。
しかし正確なレベルの測定は困難で、分類には不確定さが伴います。
そのため現在、病因論と同じで言葉としては使いますが、学術的には積極的に用いられていません。
あわせて読む
-

-
病態水準をわかりやすく。精神症状の「重篤さ」の3レベル
「病態水準」の解説。
続きを見る
DSMによる診断

DSMは、「症候論」にもとづく分類をします。

症候論とは、「観察できる症状」により精神疾患を分類する考え方。
つまり定められた各症状をチェックし、該当する症状が規定数以上あれば、その精神疾患が診断されるという仕組みです。

DSMでは統一した診断を可能にすることを目指しています。
最新版のDSM-5の特徴

最新版である「DSM-5」が、アメリカ精神医学会発表されたのが2013年。
DSM-5では、精神疾患を22のカテゴリーに分けて解説しています。
なお、4版までとの大きな違いは、
- 多軸診断を廃止した。
- 「広汎性発達障害」を廃止。「自閉スペクトラム症」として整理。
という点です。

参考:高橋三郎・大野裕監訳
「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」
ICDという診断基準

DSM以外の精神疾患の分類マニュアルとしては、WHO(世界保健機構)が発表している「ICD」があります。

日本では、「国際疾病分類」とも呼ばれてるよ。
DSMとICDの違い

DSMとICDの違いとして挙げられるのは、
- ICDは精神疾患だけの分類ではない。
- 病因についても触れている。
(病気全般)
といった点です。
現在は、1990年に発表された第10版『ICD-10』が用いられています。


現在ICD-11は、世界各国で病名など国内適用に向けた準備が進められています。
まとめ~DSM~

最後にもう一度「DSM」のポイントをまとめます。
DSMのポイント
DSMとは、
- アメリカ精神医学会が作成
- 精神疾患の分類・診断マニュアル
DSMの特徴は、
- 症候論にもとづく(×病因論)
- 観察可能な症状に注目
- 客観的である
- 操作的診断基準
=該当症状が規定以上かチェック
DSMが目指すのは、
- 統一した診断を可能にすること
DSM-5の特徴は、
- 多軸診断を廃止した点
- 広汎性発達障害を自閉スペクトラム症に整理した点
以上、DSMについての解説でした。
ご参考にさせていただいた書籍
本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。