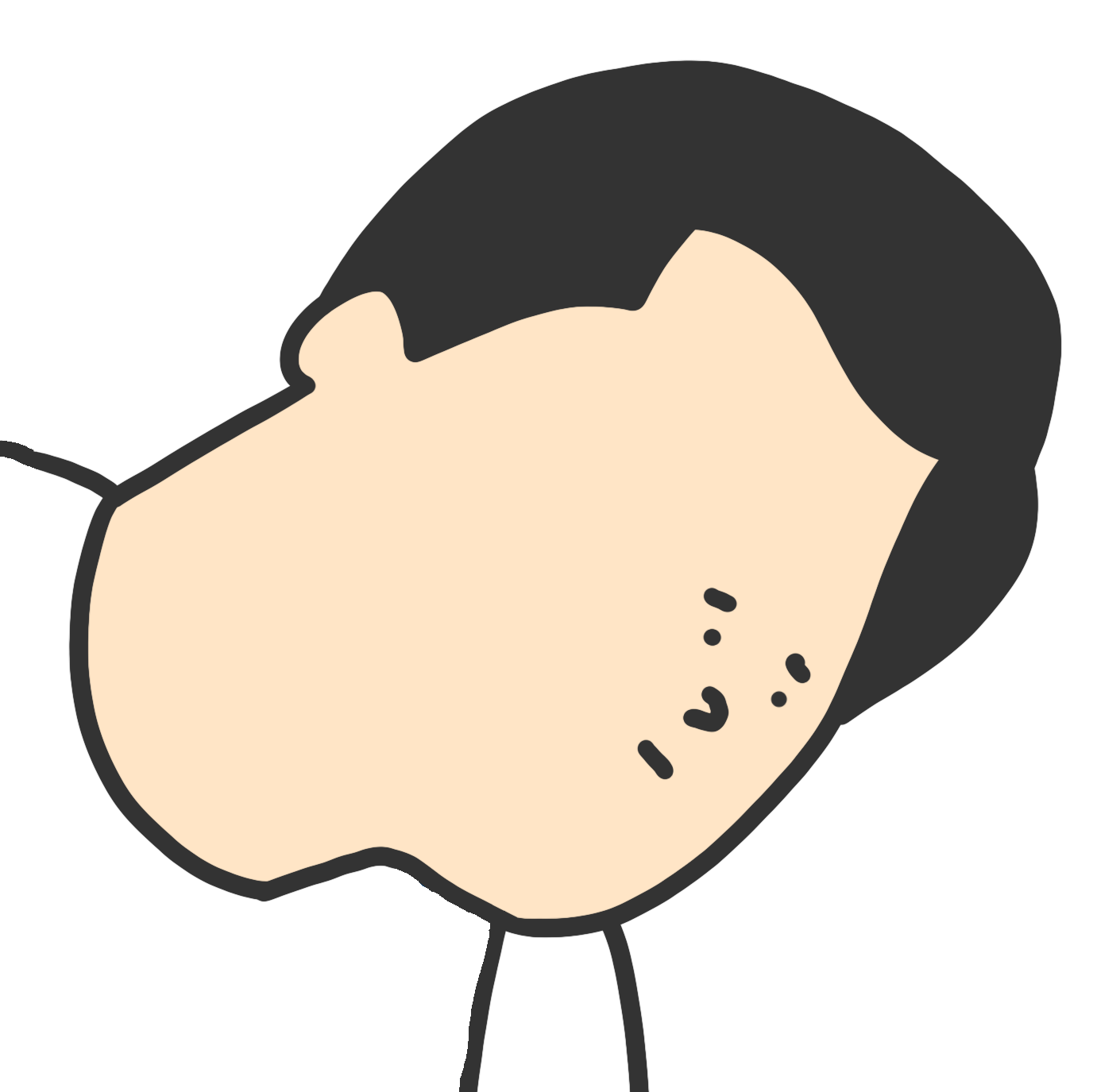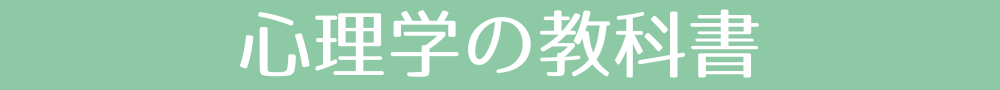心理学用語
anxiety disorder
不安症
obsessive complusive disorder
強迫症

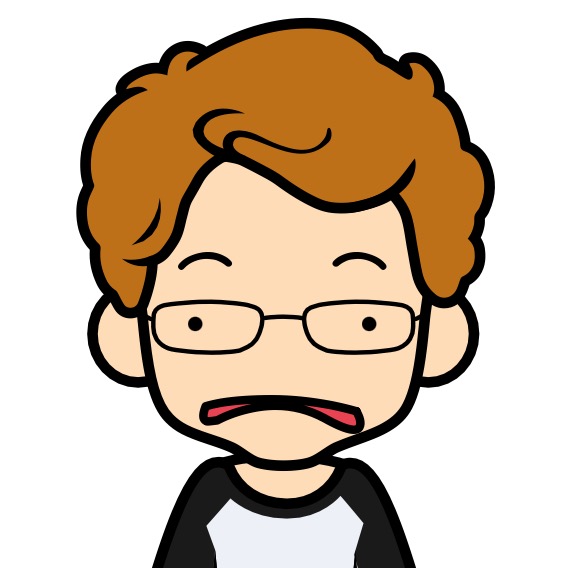
「不安症」とは、過度な不安・恐怖によって生活に支障をきたす精神疾患です。
不安症には「パニック症」や「恐怖症」など、様々な下位疾患があり、それらをまとめて「不安症群」と呼びます。

今回はこの「不安症群」を理解するために、
この記事でわかること
- 代表的な不安症について
- 「強迫症」について。
パニック症・恐怖症・全般性不安症
をご説明していきます。
代表的な不安症
不安症群の代表的な疾患の、「症状」と「求められる援助」をご紹介していきます。
パニック症

●症状
不安症の一つであるパニック症は、「パニック発作」を主症状とする精神疾患です。

この強烈な発作を経験すると、また起きたらどうしようという「予期不安」も強くなります。
この予期不安により公共の場所をさける、「広場恐怖症」を併発することも多くあります。
「広場恐怖症」とは、
公共交通機関、広い空間や狭い空間、混雑したところ、外出先で1人でいる時といった状況の内2つ以上で、過度な恐怖・不安を体験している状態。参考文献:DSM-5 「精神疾患の分類と診断の手引」
「動悸(どうき)」とは、
心臓の鼓動がいつもより激しく打つこと。
●求められる援助
パニック発作に対しては薬物療法(抗不安薬)がもちいられます。
また予期不安や広場恐怖に対しては、薬物療法(抗うつ薬・SSRIなど)や行動療法・認知行動療法が主に用いられています。
恐怖症

●症状
「特定の対象」に対する不合理な恐怖を主症状とします。
【代表的な恐怖症】
| 特定の対象 | 名称 |
| 公共の場や雑踏 | 広場恐怖症 |
| 他者からの注目 | 社会(社交)恐怖症 |
恐怖の対象として他に、高所・閉所・動物などもあげられます。
●求められる援助
恐怖症への援助としては、精神分析療法・エクスポージャー・認知行動療法・薬物療法などが現在用いられています。
全般性不安症

●症状
全般性不安症は、毎日の生活の中で漠然とした過剰不安や心配を慢性的に持ち続ける病気です。
パニック症や社会恐怖症(社交不安症)などは対象が明確ですが、全般性不安症は不安を感じる範囲が広く特定できないことが特徴です。
また症状がすすむと、睡眠障害をきたしたり、日常生活をこなすことが困難になってきます。
●求められる援助
不安の対象が特定されていないので、援助はとても難しいものとなります。
薬物療法や認知行動療法が有効とされていますが、実証研究は多くありません。

強迫症

「強迫症」は、以前は不安症に含まれる病気でしたが、DSM-5から「強迫症および関連症群」として独立しました。
●症状
持続する「強迫観念」と、強迫観念によって起こる「強迫行為」を繰り返すことを主症状とします。
強迫症の例
- 自分の手は汚い=強迫観念
- 何度も手を洗う=強迫行為
- 鍵を締め忘れたかも=強迫観念
- 何度も確認してしまう=強迫行為
強迫行為は強迫観念による不安を軽くするために、儀式的に繰り返してしまう行為になります。
本人も非合理だとわかっているのに、やめることができず、とても疲労してしまうため、うつ病などを併発することも多くなってきます。
●援助
現在はエクスポージャーなどの行動療法が主流です。

また薬物療法(SSRI)が用いられることもあります。
まとめ~不安症~

最後にもう一度「不安症・強迫症」のポイントをまとめます。
不安症・強迫症のポイント
不安症とは、
- 「不安」を主症状とする病気。
- さまざまな下位疾患がある。
- 不安症群としてまとめられる。
代表的な不安症は、
- パニック症
- 恐怖症
- 全般性不安症
など
強迫症とは、
- かつては不安症の一つだった。
- DSM-5から独立した。
- 非合理な強迫観念と強迫行為を繰り返す。
以上、「不安症・強迫症」についての解説でした。
ご参考にさせていただいた書籍
本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。